平成28年7月10日(日)第二回「松風の会」 叡山電車
- 木津宗詮

- 2019年3月3日
- 読了時間: 3分

平成28年7月10日(日)
第二回「松風の会」
於:叡山電車内
第二回「松風の会」
梅雨空の合間、お天気に恵まれ、京都・出町柳ー八瀬間を結ぶ叡山電車車内にて、第二回松風の会が開催されました。 卜翠会の後援を頂き、木津宗詮宗匠に助言を頂きながら卜翠会社中の大畑匡正と吉田正和が亭主を担当致しました。
満席のお客様を乗せた貸切電車は出町柳駅を11:40定刻どおり出発。
八瀬へ向かう車内では、建仁寺での四頭茶会の様子をプロジェクターにて映写し、木津宗詮宗匠から四頭茶会の流れをレクチャーして頂きました。<茶の湯研究「四頭茶会」参照>
緑豊かな景色をゆられること約15分、目的地の八瀬比叡山口へ到着。 到着駅では水屋や二服目のお茶を担当する社中が皆様をお迎えしました。
「七夕」の趣向に飾られた車内は、床の間を車内の吊り広告に見立てて、この日の為に揮毫頂いた南宗寺田島老大師による「耿々星河欲曙天」。 笹にかかる短冊は有隣斎宗守夫人の澄子さん。 手前には梶の葉を浮かべた水鏡が置かれました。
一服目の茶席は、先ほどレクチャーのあった「四頭茶会」の作法に則っての茶席。
四人の正客の座るべき位置を示す花が置かれ、 お菓子は春慶塗りの縁高に京都鶴屋製「天河」と椿の葉の上に大徳寺納豆。
正客には右手に縁高、左手に天目茶碗を天目台を持ちお出しする。
相伴客には縁高を長方形の長盆に人数分乗せて出す。また天目茶碗を天目台に乗せ予め抹茶を入れて曲盆で出す。
客は天目茶碗を持ったまま、そこに浄瓶でお湯を注ぎ茶筅で点てる。四頭茶会にできるだけ似せた形でお茶をお出ししました。
二服目は、柳斎宗詮宗匠書の「一服一銭」がかけられ「一服一銭」の趣向での茶席。
<茶の湯研究「一服一銭」参照>
<行事報告「第一回松風の会」参照>
第一回松風の会の時と同様、一服一銭は川崎泰大を主に、 作務衣を身にまとい、宮廷シーンでよく見かける「紗帽(サモ)」風の帽子をかぶり、 干菓子を配りながら入場した後、次々に茶を点てながら、皆様へお出しし、賑やかで楽しいお席となりました。
点心は、電車での茶会ということで、京都で昔から駅弁をつくっておられる萩の家さんにお願いして、昔ながらの経木の香りを感じる駅弁をこの日の為に少しアレンジしてご用意。また、缶ビールにワンカップで日本酒をお出しするなどして電車での食事の雰囲気を味わって頂きました。 岐路、揺られながら車内アナウンスを参加者のお子さんが担当してくれるなどし、 終止笑い声の絶えない車内でした。
次回は9/15(木)中秋の名月を趣向に、京都・祇園四条のロシア料理「キエフ」にて 第三回松風の会を企画いたします。
流儀やお茶の経験に関わらず、多くのご参加をお待ちしております。
(大畑匡正・吉田正和記)










































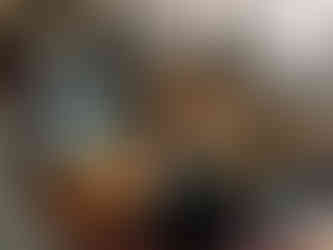



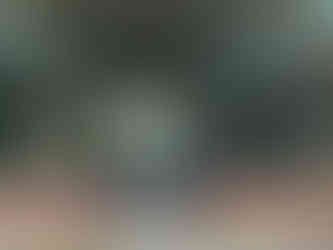

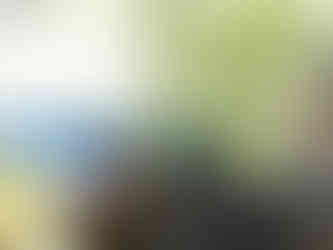



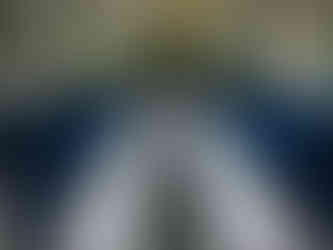





















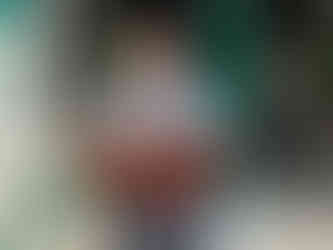















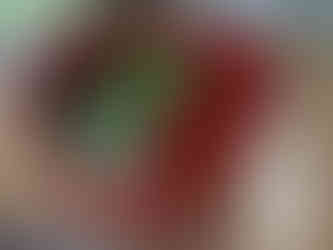





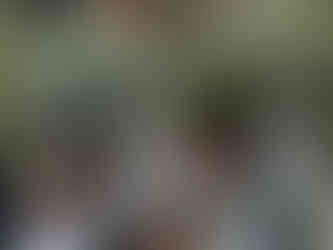















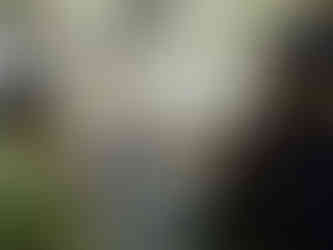



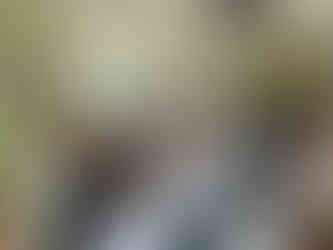











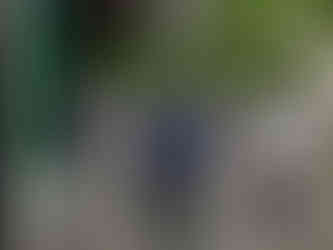


















Comments