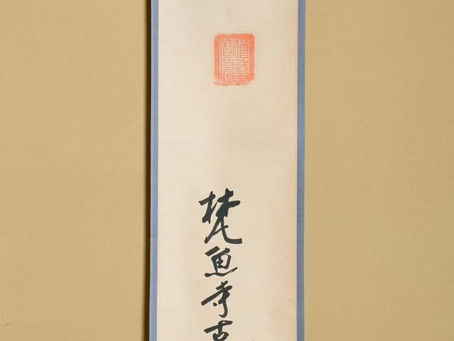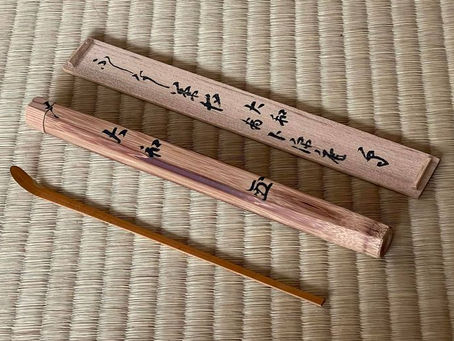top of page
検索
2代得浅斎宗詮15 跡見花蹊と得浅斎の交流2
文久2年(1862)8月5日に、「梶木町十七吉子の六日さりにて、父さま行れ、一更ニ帰られ候」とある。8月1日に3代聿斎宗泉(宗詮)が誕生している。この記述の十七吉となきちは3代宗詮の幼名である。「六日さり(だれ)」とは、昔は出産を穢れの一つとされ、産後3日目に産婆または身内...

木津宗詮
2022年8月2日読了時間: 4分
2代得浅斎宗詮14 跡見花蹊と得浅斎の交流1
『跡見花蹊日記』には、茶の湯以外での花蹊と得浅斎との交流が多く認められている。文久元年(1861)の6月15日の項には、次のような記述がある 私、木津さまへ参り、お千枝さまの舞ノ地 致し、暫遊んで帰り候。 お千枝とは明治12年(1879)に亡くなった遊心と考えられる。この日...

木津宗詮
2022年7月29日読了時間: 4分
2代得浅斎宗詮13 跡見花蹊と得浅斎の交流
『跡見花蹊日記』には、茶の湯以外での花蹊と得浅斎との交流が多く認められている。文久元年(1861)の6月15日の項には、次のような記述がある 私、木津さまへ参り、お千枝さまの舞ノ地 致し、暫遊んで帰り候。 お千枝とは明治12年(1879)に亡くなった遊心と考えられる。この日...

木津宗詮
2022年7月26日読了時間: 7分
2代得浅斎宗詮12 跡見花蹊の茶の湯
跡見花蹊が得浅斎にいつ入門したのかは不明であるが、『跡見花蹊日記』の文久元年(1861)6月1日の項に、 此八ツ時より木津さま御茶之湯に参り とあるのが初出である。花蹊二21歳の時である。その後、8月14日には、 新三郎さまと同道にて木津へ参り、竹の四...

木津宗詮
2022年7月22日読了時間: 3分
2代得浅斎宗詮11 花蹊の画芸
花蹊は教育者としてだけでなく、日本画家・書家としての側面も著名である。明治5年(1872)と26年(1893)に明治天皇の御前揮毫の栄誉を賜っている。中之島在住時分の花蹊は、茶の湯だけでなく、得浅斎と画においても関わりが深かった。文久元年(1861)5月28日、漢学の師であ...

木津宗詮
2022年7月19日読了時間: 1分
2代得浅斎宗詮10 木津家と跡見家
花蹊の父重敬は松斎同様木津村出身で、跡見家の先祖が創建し一族が代々住職を勤める菩提寺である唯専寺(浄土真宗本願寺派)は松斎の実家である願泉寺とは通りを挟んだ隣に位置している。跡見家もその付近に屋敷を構え、重敬と松斎は旧知の仲で、また茶の湯を松斎に師事したと考えられる。また、...

木津宗詮
2022年7月15日読了時間: 3分
2代得浅斎宗詮9 跡見花蹊
日本で最初の私立女子学校を創設し、また日本画家であり書家でもあった跡見花蹊あとみかけいは得浅斎の門下の一人として武者小路千家の茶の湯を学んでいた。跡見学園のホームページによると、跡見花蹊は天保11年(1840)、摂津国木津村(大阪市浪速区)の寺子屋を営む父跡見重敬(しげよし...

木津宗詮
2022年7月13日読了時間: 2分
2代得浅斎宗詮8 相伝茶事
この当時の得浅斎の茶事の記録が数点残されている。その一つに安政6年(1859)11月7日に平瀬露香以下7名に「小習(こならい)」の相伝茶事を行ったことが、平瀬露香の他会記『茶燕録』に記されている。紀州公から拝領の粟田焼の円香合で盆香合の点前をし、同じく松平不昧から拝領した楽...

木津宗詮
2022年7月8日読了時間: 4分
2代得浅斎宗詮7 『鐘奇斎日々雑記』に記された茶事
岩永文禎の『鐘奇斎日々雑記』には、万延元年(1860)11月二21日の茶事の会記が記録されている。 二畳中板西手仏間円相立サン四枚セうじ有、上に(図)如此まど有也、火トウ口反故張 木津氏へ茶事ニ行 客拙、北風、□□、山下、□□、□□□ 床 大灯国師歌沢庵書 夫奥證書...

木津宗詮
2022年7月5日読了時間: 2分
2代得浅斎宗詮6 家族の不幸
前出の通り、松斎(歓深院降龍)が安政2年(1855)の元旦に亡くなり、2月5日に得浅斎は喪主として本葬を勤めている(『鐘奇斎日々雑記』)。この時、得浅斎は36歳の働き盛りであった。同十二日には恒例の利休忌を卜深庵で勤めている。得浅斎は喪中にも関わらず、流祖利休の追善の茶会を...

木津宗詮
2022年7月1日読了時間: 2分
2代得浅斎宗詮5 伊達千広と睦奥宗光
得浅斎は治宝の信任が厚く寺社奉行や勘定奉行等の要職を歴任し、紀州藩の藩政改革を推進し、藩内の尊皇論を主導した伊達千広(だてちひろ)・宗広(むねひろ)と親交を結んでいた。なお、宗広は治宝没後、その側近が一斉に粛正された時、田辺(和歌山県田辺市)に10年近く幽閉され、のち脱藩し...

木津宗詮
2022年6月28日読了時間: 2分
2代得浅斎宗詮4 紀州家仕官
得浅斎も松斎同様紀州家に仕官している。その時期の詳細は不明であるが、『高松侯上使日記』の嘉永7年(1854)1月二25日に「宗隆主人屋敷ニ出勤」とあり、どのような役職に就いていたかはわからないが、この時点で確かに紀州家に仕えていたことがわかる。...

木津宗詮
2022年6月24日読了時間: 2分


御庭焼仁清作掛絡香合
一乗院(橘御殿)は奈良興福寺の門跡の一つです。歴代の門跡は近衛家の子息または親王が門跡となり明治にいたりました。同院は明治にいたり神仏分離により廃され官没されました。宸殿、殿上等の建物は県庁舎に使用され、のちに裁判所に転用されました。現在は唐招提寺に移築され、同寺の御影堂と...

木津宗詮
2022年6月12日読了時間: 2分
bottom of page